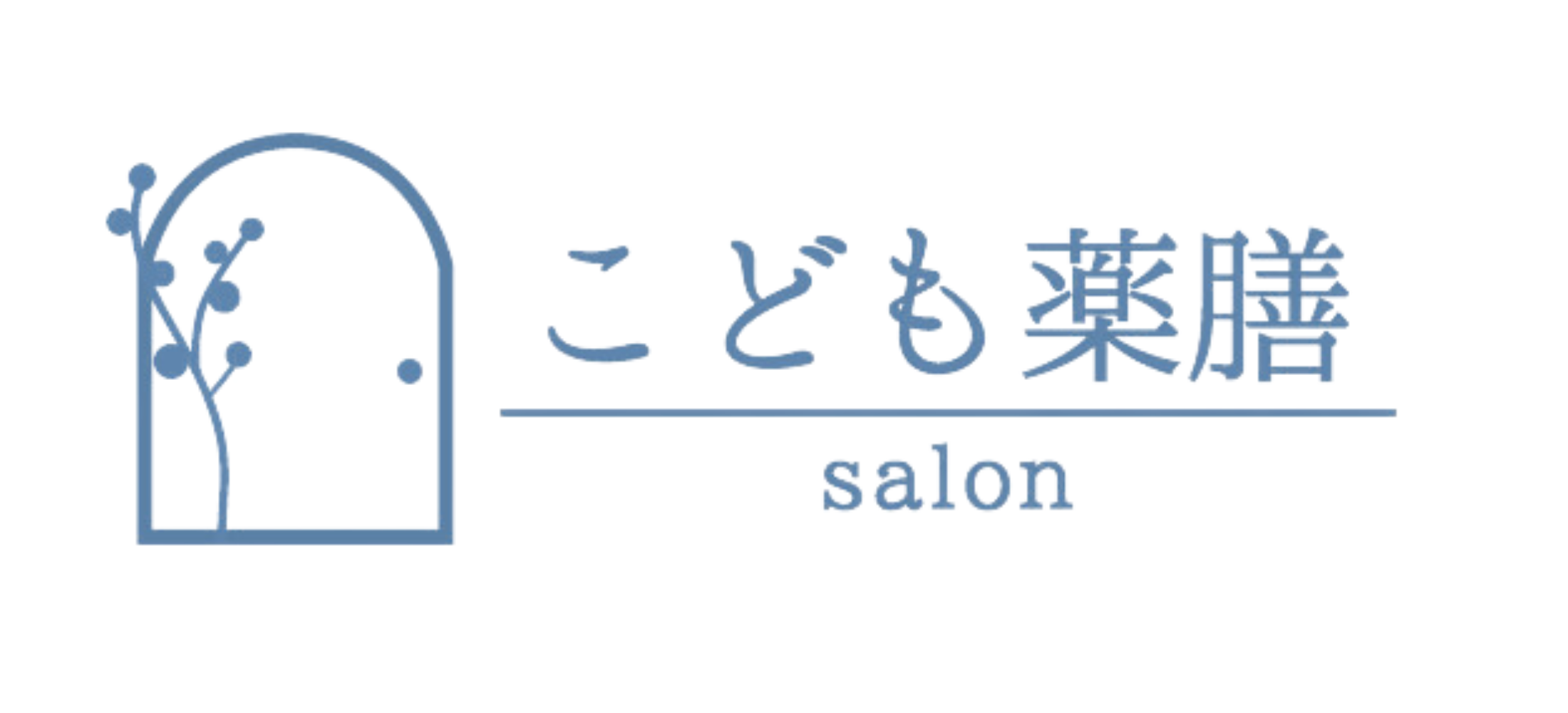子供が野菜を嫌うのはなぜ?薬膳で考える偏食の理

「野菜を食べてくれないんです」
これは、多くの親御さんが抱える悩みのひとつです。特にピーマンやほうれん草、トマトなど、独特の苦味や酸味、食感を持つ野菜は、子供たちが避けがちな食材としてよく挙げられます。
薬膳の視点から見ると、子供が野菜を嫌う背景には、味覚の鋭敏さや体の未発達な消化機能、そして精神的なバランスなど、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。
味覚が鋭い子供たち
子供の味覚は、大人よりもずっと敏感です。とくに「苦味」「酸味」「えぐみ」など、野菜特有の風味に対しては強く反応してしまうもの。実際、ピーマンの青臭さやトマトの酸味、ほうれん草のえぐみに顔をしかめる子は少なくありません。
これらの野菜の味は、食べ物が腐敗している、毒性があるものと似ていることから、子供は経験値の低さや本能的な部分で拒否してしまっていることも考えられます。
消化機能の未熟さが影響
薬膳では、消化吸収を司る「脾(ひ)」の働きが、子供はまだ十分に発達していないと考えられています。繊維質の多い野菜や、体を冷やす性質の食材は、未熟な脾にとって負担となりやすいのです。つまり、「食べない」ことは「今の体には受け入れられない」という無意識のサインでもあります。
実際に、嫌いな食材を見ていくと、その子に必要がない食材の効能だったりすることが多々あるので、驚きです。
心の状態も偏食に影響する
さらに、薬膳では「気の巡り」も大切な概念のひとつ。子供がストレスや不安を感じていると、「気滞(きたい)」と呼ばれる状態になり、消化機能や食欲に影響を与えることがあります。無理に食べさせようとすると、心身のバランスが崩れ、かえって食べ物への苦手意識が強まってしまうのです。
「食べてほしい!」というママからの強すぎるアプローチが、心の負担になってしまう場合も。。。
無理に食べさせない薬膳で考えるアプローチ法

「野菜を食べさせなきゃ」というプレッシャーに、日々悩んでいませんか?
でも、薬膳の視点では、無理に食べさせることは推奨されません。
むしろ、「食べない=悪」ではなく、「今の体に合っていない」というメッセージとして受け止めることもできます。
食べないことにも意味がある
たとえば、風邪の引きはじめに「おかゆが食べたくなる」、暑い日に「冷たい果物を欲する」など、体はその時々で必要なものを自然と選んでいます。子供も同じで、体調や気分によって食の好みが変化するのは当然のことです。
今は受け入れられない食材でも、体が整い、必要だと感じたときには自然と口にするようになります。焦らず、時間をかけて見守ることがこども薬膳で考えるアプローチ法です。
克服ではなく「整える」ための工夫を
薬膳では、「克服」よりも「調和」を重視します。
苦手を無理に消すのではなく、今の体に合った食材で栄養や働きを補っていく。これが、体質に寄り添う薬膳の考え方です。
苦手な野菜は“効能”で代替できる

野菜にはそれぞれ、「体を温める」「冷ます」「気を巡らせる」「潤す」「血を補う」など、独自の働き(薬膳効能)があります。薬膳では、こうした「はたらき」を軸に食材を選びます。
つまり、苦手な野菜を無理に食べさせる必要はありません。同じ“効能”をもつ別の食材で代替することで、子供の体調や成長をサポートできるのです。
たとえば、ピーマンが苦手な子には、気を巡らせる作用のある「柑橘類」や「にんじん」を少量使ってみる。トマトが苦手でも、同じように胃の熱を冷ましてくれる「ごぼう」や「きゅうり」を取り入れる。こうした工夫なら、子供の負担を減らしながら薬膳の効果を活かせます。
子供の苦手をカバーする薬膳的代替食材リスト
よくある苦手野菜と、それを代替できる薬膳的食材の例をまとめました。
| 苦手な野菜 | 主な苦手理由 | 薬膳効能 | 代替食材の例 |
|---|---|---|---|
| ピーマン・パプリカ | 苦味・青臭さ | 気を巡らせる、胃をすっきりさせる | 柑橘類、にんじん、キャベツ |
| トマト | 酸味・皮や種の食感 | 熱を冷ます、潤す、胃の働きを助ける | きゅうり、ズッキーニ、ごぼう |
| ほうれん草 | えぐみ・繊維質 | 血を補う、体を潤す | ぶどう、牡蠣、豚肉 |
| ブロッコリー | 花房の食感・香り | 脾を補う、体力を整える | 舞茸、さつまいも、キャベツ |
| 根菜(ごぼう) | 土の香り・硬さ | 熱を冷ます、腸を潤す | こんにゃく、えのき、バナナ |
このように、「似た機能」「似た味・香り・食感」「見た目の親しみやすさ」を意識すると、子供にも受け入れられやすくなります。
食べる意欲を引き出す親子の関わり方

代替食材を取り入れるだけではなく、親子の関わり方も“食べる意欲”に大きく影響します。
一緒に選ぶ・一緒に作る
スーパーで「どれ入れてみる?」と聞いてみたり、料理中に子供に野菜をちぎってもらうだけでも、食材への親しみが湧きます。「自分で選んだ」「自分が作った」という気持ちが、食への意欲につながります。
食材リストを“遊び”にする
薬膳的代替食材をリストにして、「今日はどれにする?」とゲーム感覚で選ばせてみましょう。冷蔵庫に貼って「体お助け野菜リスト」と名付けるのも楽しい方法です。
ネーミングの工夫でワクワク感UP
たとえば、「ヒーローパワーサラダ」「おなか元気スープ」など、ユニークな名前にするだけで、子供の関心がぐっと高まります。味覚だけでなく、言葉やイメージの力も、子供の“食べたい気持ち”を後押しします。
まとめ|子供の体と心に寄り添う食材選びで“食べる”が楽しくなる

子供が野菜を食べないと、不安になったり、つい「なんとかして食べさせよう」と思ってしまいがちです。でも、薬膳の知恵に触れると、「無理しない」という考え方がいかに大切かに気づかされます。
「食べない」ことには、体からのサインが隠れています。代替食材を使って“整える”という工夫は、「嫌いなものをごまかす」のではなく、「今の体に合った選択をする」ということ。
そして、親子で楽しみながら食と向き合う工夫が、子供の心と体の成長をゆるやかに支えてくれるのです。
今日の食卓が、ちょっと楽しく、ちょっと優しい時間になりますように。
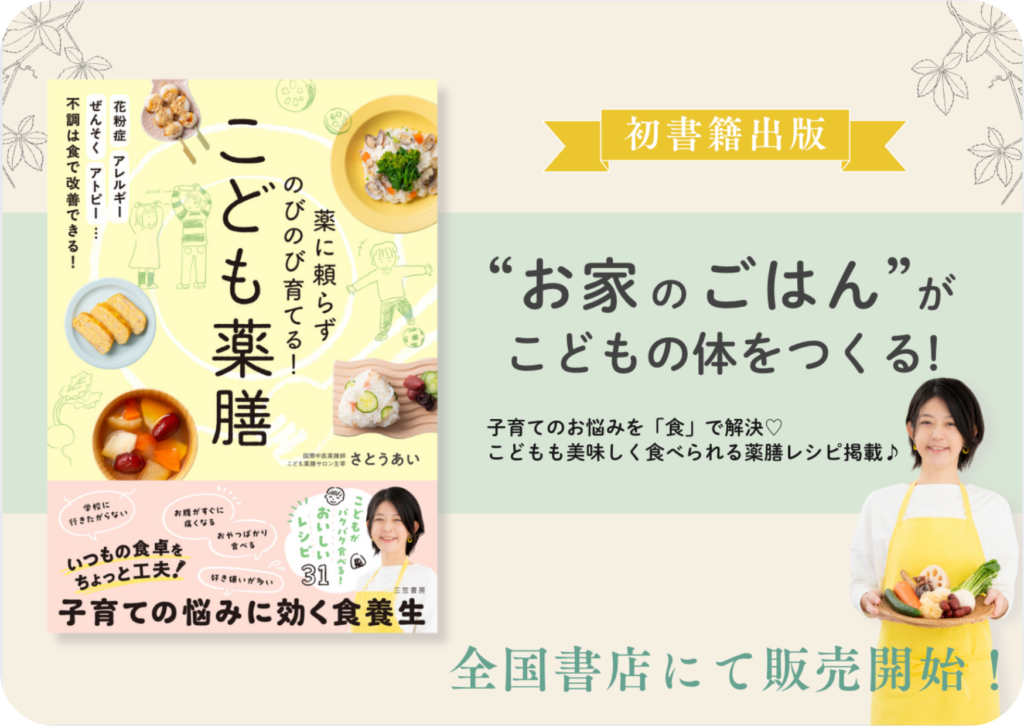
食べることに興味を持ってもらえる「きっかけ」作りは、とっても大事!書籍にはそんなヒントがいっぱい♪